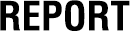「作品、表現と人 ―アートとしての可能性」
BiG-i×Bunkamuraアートプロジェクト スペシャルトーク
渋谷ヒカリエ8/ コミッティ勉強会 2024年2月27日(火)19:00〜20:30
渋谷ヒカリエ「8/」は8/で活動するディアンドデパートメント、コクヨ、アートフロントギャラリー、アンドコー、東急文化村、東急で構成される「8/コミッティ」により共同で運営を行っています。8/コミッティでは、コミッティメンバーが持ち回りで企画し、それぞれが今何に興味を持ち、どのような活動をしているかシェアしながら相互理解を深める勉強会を定期的に開催しています。
今回は、2024年8月30日から9月9日の期間、Bunkamura Gallery 8/で開催される「BiG-i×Bunkamuraアートプロジェクト」の展覧会に先駆けて、ゲストに、国際障害者交流センター ビッグ・アイの鈴木京子副館長、美術家でアートディレクターの中津川浩章さん、東京藝術大学名誉教授の秋元雄史さんの3名をお招きしトークセッションを開催。障害のある方が制作したアート作品、時代とともに変化する活動や、近年絶えず高まるアートとしての可能性とそのあり方、私たちの心を打つ作品の力とその背景に迫ります。Bunkamuraが国際障害者交流センター ビッグ・アイとともに始動した「BiG-i×Bunkamura アートプロジェクト」。障害のある方が制作したアート作品を対象に、昨年、第1回作品募集を行いました。
応募作品は国内外合わせて1400点を超え、書類選考の一次審査、実際に作品現物を見る二次審査を経て、81点を選出。秋元雄史さん(東京藝術大学 名誉教授)、上田バロンさん(アーティスト / AI BEARクリエーター)、エドワード・ M・ゴメズさん(brutjournal 創刊者 兼 編集長)、中津川浩章さん(美術家 / アートディレクター)と、国際障害者交流センター ビッグ・アイ、Bunkamuraにより選出した受賞・入選作品は、「Bunkamuraオフィシャルサプライヤースペシャル BiG-i×Bunkamuraアートプロジェクト 第1回 受賞・入選作品展」として、2024年8月30日(金)から9月9日(月)の期間、Bunkamura Gallery 8/での展覧会にて展示し、ご紹介します。
このトークセッションでは、審査員を務める3名をお招きし、それぞれの視点を交えてお話をいただきました。
鈴木 国際障害者交流センターの副館長の鈴木京子です。
国際障害者交流センターは、2001年大阪府堺市にオープンした施設です。主な活動は、障害者の芸術活動の支援を中心に、ワークショップ、公演制作、展覧会などを行っています。障害のある人たちの芸術活動を通じて、新たな価値の創造と、誰もが多様な選択肢を持ち、幸せな時間を持続できる社会を普及させることをコンセプトにしています。
美術活動の一つが「BiG-i×Bunkamuraアートプロジェクト」です。2011年から続く国際公募展で、国内外の障害のある方を対象にしています。2023年度からBunkamuraさん主催の事業になりました。もう一つの看板となる事業が「about me」です。この展覧会は賞などに関係なく、対話を重ねて選択した作品を通じて作家さんやその周縁にいる人たちを紹介する展覧会です。作品を作った人の背景、普段何をしているのか、何に喜びを感じ、どんなことが苦手なのかなどを、作家さん本人や福祉施設の支援員の方々と対話を重ねていき、作家自身と表現の関係性を可視化していくことに重点を置いています。
中津川 美術家でアートディレクターの中津川です。ざっくり仕事をご紹介します。
まずは、アーティストとしての活動です。これまでずっと作品を制作し国内外で発表してきました。上海、メキシコなどでの美術展、フィンランドでは公立ロヴァニエミ美術館で展覧会をやり、国内では毎年個展を行っています。コロナ禍のあいだは、毎日大量の水彩ドローイングに没頭しまして、それをまとめて長野のギャラリーで展示しました。
そして、アートディレクターとしての活動、展覧会を作るキュレーションの仕事もやっています。川崎市 岡本太郎美術館で開催した「岡本太郎とアール・ブリュット」展では、岡本太郎と特別支援学校の子どもたちの作品を一緒に展示しました。批判もあるだろうと思っていましたが、かえってとても分かりやすかったと感想をいただきました。
アートワークショップも長年やっています。保育園や小学校で子どもたちと作品を作り、特別支援学校でも100人ぐらいが参加する大きなワークショップを15年ほど続けてきました。
また、神奈川県小田原市にある社会福祉法人アール・ド・ヴィーヴルという事業所で、立ち上げから運営に関わっています。アート活動の支援と、障害のある方たちの作品を社会につなぐためのスキーム作りをしています。
秋元 「BiG-i×Bunkamura アートプロジェクト」審査員の一人、秋元です。
主な仕事は現代アートのキュレーションです。直島のアートプロジェクトを経て金沢21世紀美術館で仕事をしていた2011年頃、鈴木さんから声が掛かって審査員を始めました。以来、日本国内だけでなく東南アジア・ヨーロッパ・中南米など世界中の幅広い作品を見てきましたが、もはや障害者アートという言葉ではつかみきれない、豊かな表現を目撃しています。
2015年から東京藝術大学 大学美術館で仕事をします。そこで「あるがままのアート-人知れず表現し続ける者たち」という展覧会を文化庁、NHKとの共催で実施します。NHKでは「no art, no life」や「人知れず表現し続ける者たち」といった番組を放映していたので、これまで障害者の創作活動やアートを知らなかった方々からも関心を持っていただけたと思います。また会場となった藝大は、プロのアーティストを養成する教育機関であり、それに付属した美術館ですから、プロフェッショナルな教育を受けた人たち、平たく言えば上手い人たちの作品を飾る場ですので、そこに、いわゆる専門的な教育を受けていない方の創作物を飾る、あるいは障害者の制作物、アートを飾るというのは、教育の場としても意味があったわけです。
学術的な視点からも意味があり、学生たちにとっても上手い下手を超えた、アートへの問いかけというものが起きた展覧会だったろうと思います。毎回そうですが、作品を支えるアートとは何か、アートとはどんな価値を持つものなのかという本質的な問いかけが生まれた展覧会でもありました。
その後、2018年から練馬区立美術館に移るのですが、そこでは2020年に「式場隆三郎 脳室反射鏡」という展覧会を開催しました。式場隆三郎は、精神科医で、民芸運動に同伴したり、白樺派に接近したりして、医業と芸術の両面から人間を眺めた研究者です。ゴッホの国内での紹介者としても有名ですし、山下清を大衆的なレベルにまで広めた人でもあります。いわゆる障害者アートの先駆的な評価者です。戦前戦後に芸術的な視点から障害者の制作するアート作品を問題にし、今日につながる業績を残しています。式場隆三郎の業績を紹介することで、既存の美術の枠組みから漏れ落ちる、人間の豊かな創造性や世界を改めて提示する機会になりました。
かつてよく言われたのですが、障害者のつくるアートは、福祉か、芸術かという議論がありました。福祉政策として語られるべきか、芸術的な価値として評価すべきかという問題です。今日でもその間で引き裂かれて制作している現場があります。また芸術として位置づけるにしても、またそれはどのような文脈で捉えるのかという問題もあります。アール・ブリュットやアウトサイダーアートと呼び、前衛美術の一流派と位置づけるのが正しいのか。あるいは、別の文脈によって位置づけていくことが必要なのか、これも考えどころです。魅力的に見える一枚の作品がやがてそれが集合して、一つの群として私たちの目の前に姿を現した時に生まれてくる意味や時代との関係といった点からも読み解かれているべき存在なのだと思います。その点から見ても、くめども尽きない豊かな場なのだろうと思います。
近年、障害のある方のアート活動に変化はあったのか?
鈴木 障害のある方のアート活動、表現活動はここ十年ですごく変化があったように感じています。お二人はどうお考えでしょうか?
中津川 確かに公募展は増えました。行政も支えるようになったので、障害のある人たちのアート活動の幅も広がったし、そうした活動をする福祉事業所も爆発的に増えています。
僕は7つほど公募展の審査員をつとめていますが、主催者によって考え方やコンセプトも違いますし、歴史や文化も含めた地域性の違いも感じます。アプローチの仕様にも多様性というか複雑さが出てきたと感じますね。
秋元 応募数が増えたのは大きい変化ですね。ビッグ・アイの公募展の醍醐味の一つは、2000を超える作品数をひたすら見ることです。作品のバリエーションも、ものすごく増えています。
始めたての頃は「見つけなくちゃ」というちょっと上からの目線が正直ありました。だけど、途中からパワーに圧倒されるというか、こちらの読解能力を試されている感じに変化してきました。
中津川 この公募展は選び方がほかと違いますよね。普通は多数決です。
鈴木 そうです、多数決にはしないんです。各審査員の先生が票を持ち、応募の全作品から一人12点ずつ選んでいただく。
中津川 まず全作品からパパパッと独断で200点ぐらい選び、そこから十分の一に絞ります。最終的に自分が責任を持てるか、言語化できるかというところで判断していくので、審査員のカラーがくっきり出ます。他の審査員から刺激を受け、自分の見方も拡張され変革しながら選んでいますね。
福祉とアートの境界線を消したい
鈴木 福祉とアートの境界線を消していけたらという想いで、 2012年から展覧会の場所としてBunkamuraさんのギャラリーをお借りしてきました。当時と今とで、アートとして変化はあったんでしょうか?
中津川 評価はかなり変わりました。公募展も福祉色が強いのもあれば、純粋にアートとして評価しようとするもの、流通することを目指すものもあり、選択肢が増えました。
審査をしていて面白いのは、精神障害、精神疾患がある人たちの作品が増えていることです。作品から現代社会が透けて見える気がします。
秋元 「GO FOR KOGEI」という工芸ベースの現代アートの展覧会をやっていますが、工芸作家や現代アーティストの作品の中に、障害ある方たちの作品も混ざった姿で紹介されています。普通にアート表現として成り立っているので、僕はあえて何もコメントしていません。
「この作家、どんな人だろう」と属性を調べたら、知的障害や精神疾患があることが分かる。それは作品の後に来る属性の一つになればいいなと思います。
鈴木 私は舞台芸術のプロデュースや制作が専門でしたが、ビッグ・アイの事業をきっかけに、美術分野の活動もはじまりました。福祉の専門家ではありませんが、障害のある人たちの芸術活動を行うには、福祉の視点も重要となります。
一方で「障害のある人のアート作品です」とわざわざ言わなくても、アートとして社会に認知されるにはどうしたらいいんだろうと思います。
二つの展覧会のひとつ、「about me」は、福祉の視点を大切にしている展覧会だといえます。医療ケアが必要な重度の障害がある方々の作品やその背景を深堀りしていく過程で自分でも芸術と福祉の間で揺らぐこともあります。
中津川 アール・ブリュットやアウトサイダーアートという概念は、西洋の美術史ではヨーロッパ現代史の流れと芸術活動の中から必然的に生まれました。精神病院に入っている人たちがセラピーで描いた作品表現を、アール・ブリュットとして一つのパッケージにしたんです。
一方、日本の障害者アートは福祉の中で生まれてきました。滋賀の近江学園で障害のある子どもたちの可能性を引き上げる表現活動として始まりました。そこから、いろいろな活動が派生して、途中からアール・ブリュットという名前を付けてブランディングした。福祉と美術の価値が合致して、交錯しながら現在に至っています。
秋元 アール・ブリュットやアウトサイダーアートという言葉は、西洋の歴史的事情と社会背景から生まれたので、そのまま日本語にはなりません。
日本から生まれた福祉とアートの現状を学術的に調査し、現場で何が起きているかを整理する必要があります。日本は福祉作業所のディレクターさんたちが創作の場を作り、その中でアーティストが育ってきているという事情から、ある種の集団性があります。
海外の専門家と日本で調査すると「どこまで一人でやっているんだ?」と言われます。西洋は個人主義にのっとっているので日本的な集団性が気になるらしい。日本の文化的、社会的事情もうまく伝えていかないといけません。
中津川 あるアメリカのアートセンターでは、障害がある人たちが作品を作っていますが、クオリティが落ちると退所することになると聞いたことがあります。
一方、日本の福祉施設では描いても描かなくても作業所を退所させることはないし、個人の幸せを優先している。そうした中から前述のアートセンターに劣らずレベルの高い作品がどんどん生まれてきている。そこになにかヒントがあると思います。
創作意欲を引き出すための周囲のサポート
中津川 秋元さんが場作りや集団性と言ったのは、体が不自由な人のために作業員がキャンバスを回したり、絵の具を溶いてあげたりすることですね。作家の表現として確立させるために、どこまで介入、サポートするか。決まり事はないので、その場の状況で考えながらやっています。
施設によっては、手を添えて描いちゃうところもあります。あとで手を加えてしまう施設もいくつか知っています。それはやっちゃいけないことですが、線引きがまだまだ曖昧です。
秋元 グレーなところもありますね。現場レベルでは助け合いの気持ちでちょっと手を添えているだけだったりするけど。
中津川 良かれと思って手を加えたことで、作品が普通になっちゃうので、僕が見たら面白くない。なにか足りない方がリアリティがあるんです。
ただ、障害のある人たちは、サポートがないとなかなか表現活動までたどり着かない。全部自分でできるかというとそうではないし、展覧会もサポートがないとできない。
そういう意味で、作業所や支援者とのコラボレーション的な要素はけっこうあって、作業所の雰囲気が作家さんと作品に反映してくる。福祉施設によって雰囲気が似てくるというのかな。おそらくサポートするときの独特の間合いとか声かけといった関係性の中で作品が生まれている。
秋元 使っている材料など基本的なものが同じなので、そこら辺は仕方がないですね。 私は施設ごとの流派のように見ています。
日本の習い事文化の延長という気もしますが、集団性が強すぎると見えないところに価値基準が張り巡らされて、作品が似通ってしまう。集団性の緩いところの方が面白いです。
鈴木 中津川さんはアーティストの立場から見て、支援員やグループによる作品作りはOKなんですか?
中津川 最初はダメかなと思いました。「本人は望んでないのに、なんでキャンバスを回すんだ」とか「水性マーカーは退色するから使わせないでください」とか色々言いました。でもそれで本人が伸びたり、新しい可能性をつかむのを見ていると、キャンバスを回すのもありだなと。こっちの思い込みや固定観念はことごとく覆されてきましたね。
ほかの公募展で「これはいい作品だなぁ」と思ったら、作者は違うのに同じようなタイプの作品がずらずら出てくることがあります。おそらく指導する人が入っている。それはあんまり面白くないなあと思う。作業所に就職するアーティストや美術大学の卒業生が増えています。結果として、介入が増えるのでしょう。
作家の内在的な可能性を引き出すのは、まわりにいるむしろ「美術」とは関係のない人たちの真摯な向き合い方や声かけだという気がするんですよね。アートを教えないというか……。先入観がない分、表現に驚く力があるんです。
鈴木 専門的な知識がない分、いろんな引き出し方のトライができるのですね。
秋元 その場で「わあ!」とか「あらっ!」みたいな面白がるリアクションは結構大事なんじゃないのかな。鋳型にはめ込んじゃうとやっぱりつまらなくなっちゃう。
表現でコミュニケーションできる、人としての豊かさ
鈴木 去年、中津川さんと「about me」の活動を通じて医療ケア施設に3回ぐらい通いました。
作業療法士さんと理学療法士さんとタッグを組んで表現活動をされていて、一日中ほとんどベッドで寝ている方が、体を動かせる装具をつけて、20分も30分もかけて描いていました。
中津川 10cm描くのに3時間ぐらいかな。動画を早送りして見ないと動いていることが分からない。
鈴木 筆先で点を打った瞬間に、周囲の支援員さんや作業療法士さんが「描けましたよ!」って声をかけている。
中津川 その時に言った言葉が「眼球運動があった!」。体が動かないから、目が動いたことで、みんな拍手して。
鈴木 周りの人の歓声や喜ぶ姿が、自由に描けない人たちにもすごく伝わっている感じがありました。だから、もっと描きたいという気持ちになっているのかなと思います。
秋元 やっぱりコミュニケーションだと思うんですよ。それぞれのやり方はありますが、眼球が動いたっていうのは、その人にとってみれば最大のコミュニケーションの瞬間なわけで。そのやり取りができることが人としての豊かさなんだろうと思うんですよね。
中津川 そこで生まれた作品は、やはりアートとしても面白いですよね。力があるし、無駄がない。あえて余白を残したという感じじゃない。その一筆しかできないから、一筆に全部込めてある。
アール・ブリュットという一般的な表現の質とは異なりますが、そこには不自由さがスパークして表現が生まれる瞬間がプロセスとして記録されている。
社会の変化に応答する表現者たち
鈴木 コロナの三年間が大きな転換期で、ここ数年、個人で応募される方がすごく増えました。人との関わりが閉鎖的になって、外に出る手段が狭まり、事業所を通じた応募ができなかったことで、個人で応募したのはないかと思っています。
秋元 表現者は社会の変化に応答しているし、社会のあり様の中で作品を作っていますね。
中津川 知的障害の方とか施設で描いている人たちも、テクノロジーや情報の影響を受けているので、やっぱり社会化されていると思います。
2000年ぐらいだと、反復で細かい点を打ったような現代アートにないタイプの作品があると、審査員の先生たちと「これ、すごいよね!」と言っていたし、入選していました。でも今、同じタイプの作品があっても、たぶんなかなか選ばれないと思うんです。前は障害特性の反映だけで面白いと思えたんですが、今は個々の表現を掘り下げたものだけが残ります。
秋元 作家さんに作品が溜まってきたので、時間軸で見えるようになってきました。一人の作家さんの作品をバーッと時系列で見ると変化が分かる。一人の人間の世界観、その人が見てきた世界がにじみ出ている。それはもうアートだよね。
中津川 そうとしか言いようがないです。だからアール・ブリュットとか障害者アートじゃなくて、アートなんだよね。そこに回帰しますね。
公募展の今後の展開
鈴木 この公募展が今後どういう展開をすれば、よりアートとして社会に価値を発信できるか。お考えを聞かせてください。
中津川 いろいろな公募展ができているし、作品がグッズやデザイン、テキスタイルに使われることも増えている。そうなると表現の深まりがすごく大切です。それは障害者アートとしてではなく、やはりアートとしての深掘りです。
社会学的に障害者アートがなぜ生まれたかというと、障害者がやっぱり社会と分離しているからだと思います。社会が分断しなかったら障害者アートというジャンルはありません。
人間として同じ表現者として見る、表現者によって表現されたものとして見る、そうなっていけば、障害者アートという名前が本当に消えるだろうし、そこまで行ったらいいなと思っています。
本を読まなくても、言葉でアウトプットができなくても、世界観が出るのがアートの面白さです。非言語のコミュニケーションが持つ大きい可能性が、障害がある人たちの表現にまだまだいっぱい詰まっている。それが人間の概念の拡張につながっていくと思います。
秋元 今後、障害ある方のアートをどうするかは、社会化していくプロセスをどう描くかだと思います。この公募展は、続けているすごさがある。どう変化していくかを俯瞰的に見る装置として、ずっと続けることに意味があると思います。
もう一つ、美術館を軸に展覧会が開かれる時期に来ていると思います。レジェンドクラスと言っていい、国際的に評価される作家さんたちが出ています。障害のあるなしに関係なく、どういう世界を描いているか、それらの豊かさをどう見ていくかが問われる時期に来ています。
一方で、グッズ開発したり、デザインに取り込まれたり、社会化する場面をうまく作り出していく。少しでも継続できるようビジネスになりお金が回る、そんな社会性を獲得していくことも必要だと思います。
質疑応答
質問者 審査員が12点ずつ選ぶと、かぶる作品はどのぐらいありますか?
鈴木 一つの作品に全員の札がついている時があります。1000点ほどの作品数に対して、持ち札が12しかないので審査員の間で相談もありますよね。
中津川 自分の独断と偏見で選んでいるつもりでも、結構かぶりますよね。「これは他の審査員が選ぶからいいだろう」と選ばないでいたら、最終的に審査員全員が外しちゃったこともあります。
秋元 「あ、やばい、じゃあちょっと誰も選んでないから、これ選んでおこう」とか、「これは僕も面白いと思いました」というメッセージを伝えておく意味合いもあるので、他の審査員とかぶるのはある。かぶりを避けようと逆から回ったり、いろいろしているんですけどね。
中津川 最後には自分の選んだものをまとめて別の部屋に持っていき、並べて見ます。そこでまた「これで大丈夫か、あれと替えた方がいいか」と悩みます。 家に帰ってからも頭から離れません。
「about me」をやろうと思ったのも、選ばれなかった作品をもう一度浮かび上がらせたいという想いからです。
受賞作品紹介
中津川浩章賞 作品名「孔雀の散歩」 作者 ほんままい
中津川 ほんままいさんは、三重県にある福祉事業所のメンバーです。知的障害があって身体の可動域が狭いとか不随意運動がある方たちは、ものすごい力で絵を描いています。力の加減がゼロから100でいうと100%全開なので、タッチがクリアです。たぶん彼女の中で孔雀のイメージみたいなものが抽象的に昇華されて、こういう形になっている。抽象的な感じと身体の行為性みたいなものが、強く結びつきそうで結びつかない、ぎりぎりの間合いを縫ってせめぎ合っているところがとても気に入った作品です。
秋元雄史賞 作品名「清らかな心」 作家名 ☆ acco・Lemuria ☆
秋元 お花のようなものを細いワイヤーで作り、レジンという透明なフィルムが繊細にかかっていて、円形の中にぎっしりと集まっている作品です。
アール・ブリュットとかアウトサイダーアートというと、現代アートの論理で見ていく作品が割と多いのですが、これはむしろ工芸ですね。手で物を作っていく世界です。その手作りの繊細さがうつくしい。
僕はこういう繊細な仕事も非常にいいと思って選びました。モノトーン調の白い空間の作品ですけれども、光が充満しているポエティックな空間になっています。作品に顔を近づけて見ると繊細だけど、何か強く美しい世界が感じられて、まさにタイトル通り「清らかな心」。すごく美しいなと思っています。
BiG-i賞 作品名「Shadow man」「NYC 2023」 作家名 Marven
鈴木 国際障害者交流センターですので、海外からの作品を選びました。カナダの作家さんです。私は美術の専門知識がないのですが、 一言で言うと「好き!」です。アートってそれでもいいのかなと思っています。海外からの応募作品も結構あったのですが、審査会場でこの作品の前に来ると何度も足が止まりました。
大きい方の作品は絵の具だけじゃなくコラージュがあって、それも面白いです。小さい方は全然色が違って、絵画としてもすごくかっこよくて素敵だなと思いました。どのように作品制作をされているか全く分からないですが、本当にかっこいいなと。部屋に飾ったらいいなと思い、選びました。
今回海外からもたくさんの応募が来たので、8月の展覧会では海外の作家さんの作品をたくさん展示できると思います。ぜひ楽しみにしてください。
勉強会を終えて Bunkamuraよりコメント
福祉とアートの境界線が消え、その可能性が広がることは、アートというもの自体の可能性の広がりでもあると感じています。日々を共に暮らす、良質なアートとの出会いの場でありたいと願う私たちが、今回の公募展を開催することの意義をあらためて考えていくとともに、ここで美しいエネルギーを放つ作品に出会い、皆様と思いを共にできると考えると、それがただただ純粋に楽しみでなりません。(Bunkamura 塙 衣都子)